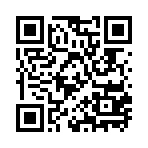10月29日30日 WAZAフェスタ 2011inしずおか 開催
10月29日(土)・30日(日)、ツインメッセ静岡で
『WAZAフェスタ 2011 in しずおか』が開催されました。

『WAZAフェスタ 2011 in しずおか』では、アートモザイク、木工や洋裁など様々な業種の職人さん達に教えて貰いながら、ものづくり体験ができる「WAZA体験コーナー」やものづくりを通じて交流を深める「WAZAの交流広場」など子供から大人まで楽しめるイベントが盛りだくさんでした。
他、会場内には以下のような競技大会や様々なコーナーがありました。
・WAZA体験コーナー
・WAZAの交流広場
・農産物加工品展示・販売コーナー
・小中学生技能競技大会
・障害者技能競技大会
『WAZA体験コーナー』では、

「アートモザイク」体験があり、小さな女の子が職人さんからアドバイスを聞き、自分だけのイメージをタイルの破片を用いて描いていました。
その制作中の彼女の横顔は、ハッとするほど真剣な眼差し。やはり、制作中は大人も子供も関係なし。
職人さんに負けず劣らずの意気込みと一生懸命さが伝わってきました。


他、「印章業協同組合」ブースでは『テン刻体験』というものがありました。
このブースは、柔らかい素材の石で自分の名前を彫刻刀を使って彫っていく体験コーナーです。
体験者は小学生低学年の児童から60歳過ぎの年長者までが並んで体験していました。


今回のこのイベント、来場・参加した児童も真剣でしたが我が子を連れてきた親御さんの方が真剣になって体験していたりする場面もありました。
「集まれ!ものづくりキッズ つくるってたのしい」がこのイベントのキャッチプレーズでしたが、『ものをつくる』って大人も子供も童心にかえる良い空間なのかもしれません。
また、『テン刻体験』でのご家族ではお父さんとお母さんが息子・娘の後ろに立ち必死にアドバイス。最終的にお父さんとお母さんが息子・娘の代わりに彫刻刀を持って成果物を子供に自慢していた場面などなど。
『もの』を『つくる』ことで、「家族の和もつくる」。そんな暖かい光景も見ることができた1日でした。
『WAZAフェスタ 2011 in しずおか』が開催されました。
『WAZAフェスタ 2011 in しずおか』では、アートモザイク、木工や洋裁など様々な業種の職人さん達に教えて貰いながら、ものづくり体験ができる「WAZA体験コーナー」やものづくりを通じて交流を深める「WAZAの交流広場」など子供から大人まで楽しめるイベントが盛りだくさんでした。
他、会場内には以下のような競技大会や様々なコーナーがありました。
・WAZA体験コーナー
・WAZAの交流広場
・農産物加工品展示・販売コーナー
・小中学生技能競技大会
・障害者技能競技大会
『WAZA体験コーナー』では、
「アートモザイク」体験があり、小さな女の子が職人さんからアドバイスを聞き、自分だけのイメージをタイルの破片を用いて描いていました。
その制作中の彼女の横顔は、ハッとするほど真剣な眼差し。やはり、制作中は大人も子供も関係なし。
職人さんに負けず劣らずの意気込みと一生懸命さが伝わってきました。
他、「印章業協同組合」ブースでは『テン刻体験』というものがありました。
このブースは、柔らかい素材の石で自分の名前を彫刻刀を使って彫っていく体験コーナーです。
体験者は小学生低学年の児童から60歳過ぎの年長者までが並んで体験していました。
今回のこのイベント、来場・参加した児童も真剣でしたが我が子を連れてきた親御さんの方が真剣になって体験していたりする場面もありました。
「集まれ!ものづくりキッズ つくるってたのしい」がこのイベントのキャッチプレーズでしたが、『ものをつくる』って大人も子供も童心にかえる良い空間なのかもしれません。
また、『テン刻体験』でのご家族ではお父さんとお母さんが息子・娘の後ろに立ち必死にアドバイス。最終的にお父さんとお母さんが息子・娘の代わりに彫刻刀を持って成果物を子供に自慢していた場面などなど。
『もの』を『つくる』ことで、「家族の和もつくる」。そんな暖かい光景も見ることができた1日でした。
2011年10月30日 Posted by s-syokunin at 17:00 │Comments(0) │取材日記
左官職人の萩原多助さん取材

藤枝出身の萩原さん、お父さんと一緒に16歳から見習いとして始めたそうです。それから程なく18歳のときに鉄筋関連の建設現場で今後の日本の建築業界で必要なノウハウを学ぶために単身で東京に向かいました。たまたま行きの電車の中で知り合った方が萩原さんの指のタコを見て声をかけてくれ、3年間その人の下で働いて静岡に戻ってきたという話を聞き、人との偶然な出会いが実は人生の方向性を決める重要なターニングポイントになる事もあるんだと、出会いの大切さを感じました。
今回はツインメッセの西館1Fの技能高等学校実習場で話を伺いました。このとき生徒さんも3名、職人技術を上げ資格試験にパスできるように実践練習をしていました。

実践練習用の壁、つまり資格の課題のために作られたもので、日々練習をすることによって資格試験の当日に緊張しすぎて真っ白にならない為に・・との配慮からのようです。(とはいっても緊張はするようですけど)。

丁寧に捏ねられた土をコテで滑らかに壁に塗っていく様子は「あれ?そんな簡単に?」と思うほど見ている人が簡単に出来るんじゃないかという錯覚を起こすくらい、何十年もこの仕事をされてきた経験が僕たちを勘違いさせます。
いざコテを持ってみて土を捏ねようとしても。
コテに土をすくって壁に塗りつけようとしても。
「あれ?」そうまったくイメージトレーニングは役に立たないようです。

萩原さんが言っていました。仕事は目で盗んで覚えるもの。上手い先輩の作業をよく見て覚えて、そして練習をする。誰も忙しいときに教えてなんてくれない。先輩たちもそうして技を磨いてきたんですよ。
また、そこから今度は人に負けないものを必ず2つから3つ持つことで周りから認めてもらえるようになる。そしていつも心に「初心忘れず」を持ち続けることが大切だそうです。



2011年10月14日 Posted by s-syokunin at 10:36 │Comments(0) │取材日記
静岡県技能競技大会 配管職種
我々素人からの眼で見るとなかなか完成品の見た目での差は分かりませんが、厳しい教官の目はしっかりとマイナスになるポイントは見えていますから、その目が近くにある環境は普段の仕事での緊張感とまた違うストレスにもなったと思います。教官に話を聞くと、もちろん完成品の配管がしっかり出来ているか?水漏れはしていないか?も当然検査します。ただその前にも服装や作業態度などもしっかり減点の対象になりますからって教えていただきました。ただ完成品を作るだけじゃなく、そのものを作る人そしてその過程も非常に大切なんですね。











2011年10月12日 Posted by s-syokunin at 16:07 │Comments(0) │取材日記
沼津:WAZAチャレンジ教室(料理) 玉子焼き&アジのタタキ
10月11日、静岡県立沼津特別支援学校 伊豆田方分校でのWAZAチャレンジ教室取材に行ってきました。まずは玉子焼きですが、今回は1人3個の玉子を使いました。やはり3個くらい使うとボリュームがあって作った感が大いに出るそうですよ。たまごの割り方も片手でやらずに両手で割ることが重要。普段簡単に片手で割ってしまいがちな卵ですが、確かに片手で横着にやって殻がボール中に入って取りにくい状況って結構あるような・・・。そのあたりも丁寧にやることが美味しく、そして成功への近道なのかなって感じました。

玉子焼き用のフライパンを中火にかけて熱していきます。油を加えてフライパンが温まってきたら少し出汁を入れてよくかき混ぜた玉子を少しフライパンに落とします。「ジュー!!」投入の合図です。まずは3分の1をゆっくり流し込みます。くるくる箸でかき混ぜながら玉子を焼いていきます。手首を上手く返しながらフライパンを使うとくるっと玉子が返ってフライパンの半分の部分に集まります。


空いた部分に油を引いて残りの玉子の半分を流し込みます。焼けた玉子焼きの下に次のトロトロの玉子を流し込んで焼いていきます。玉子を返す作業が手首のスナップを利かせないといけなくて、非常に悪戦苦闘の生徒さんたち。そちらに夢中でフライパンがコンロから遠く離れてしまい「もうちょっと火に近づけて!」先生に言われながら、でも非常にまじめで楽しそうな笑顔でいっぱいでした。最後に残った玉子も加えて大きなフワフワの厚焼き玉子の完成です。「いい匂いだなぁ・・・。」


さて続いては?アジのタタキ!内臓を取る部分は時間のの関係上、先生である職人さんがやってくれましたが、三枚卸の作業はもちろんみんな自分でやらないとね。後で実は担任の先生たちも挑戦!「あれ?結構大変そうですね(笑)!」





さて!アジのタタキは出来ました。でも頭の部分と尻尾の部分残しておいたのは?そう!料理するなら本格的にやりましょう!お店屋さんの料理みたいになってきましたよ。




魚を三枚に卸した時にでた骨、あらの部分ありますよね。今回はそれでお味噌汁も作りました。油揚げ、豆腐、長ネギがたっぷり入った具だくさんのお味噌汁。なんかパーティーみたいで楽しそうだなぁ。





今回の料理教室で使ったフライパンは生徒さん一人一つもらえるそうです。みんな家に帰って家族に作ってあげるのかな?最後に先生が、「みんな最初は上手に出来ません!もちろんここに今日来てくれた先生たちも最初は下手でした。でも毎日練習して努力して今があります。皆さんも今日ここで習ったことを是非復習してみてください。」何事にも当てはまる言葉ですよね。肝に銘じておかないと・・・。そう感じました。きっと生徒さんたちもそう思ったんじゃないかな。

玉子焼き用のフライパンを中火にかけて熱していきます。油を加えてフライパンが温まってきたら少し出汁を入れてよくかき混ぜた玉子を少しフライパンに落とします。「ジュー!!」投入の合図です。まずは3分の1をゆっくり流し込みます。くるくる箸でかき混ぜながら玉子を焼いていきます。手首を上手く返しながらフライパンを使うとくるっと玉子が返ってフライパンの半分の部分に集まります。


空いた部分に油を引いて残りの玉子の半分を流し込みます。焼けた玉子焼きの下に次のトロトロの玉子を流し込んで焼いていきます。玉子を返す作業が手首のスナップを利かせないといけなくて、非常に悪戦苦闘の生徒さんたち。そちらに夢中でフライパンがコンロから遠く離れてしまい「もうちょっと火に近づけて!」先生に言われながら、でも非常にまじめで楽しそうな笑顔でいっぱいでした。最後に残った玉子も加えて大きなフワフワの厚焼き玉子の完成です。「いい匂いだなぁ・・・。」


さて続いては?アジのタタキ!内臓を取る部分は時間のの関係上、先生である職人さんがやってくれましたが、三枚卸の作業はもちろんみんな自分でやらないとね。後で実は担任の先生たちも挑戦!「あれ?結構大変そうですね(笑)!」





さて!アジのタタキは出来ました。でも頭の部分と尻尾の部分残しておいたのは?そう!料理するなら本格的にやりましょう!お店屋さんの料理みたいになってきましたよ。




魚を三枚に卸した時にでた骨、あらの部分ありますよね。今回はそれでお味噌汁も作りました。油揚げ、豆腐、長ネギがたっぷり入った具だくさんのお味噌汁。なんかパーティーみたいで楽しそうだなぁ。





今回の料理教室で使ったフライパンは生徒さん一人一つもらえるそうです。みんな家に帰って家族に作ってあげるのかな?最後に先生が、「みんな最初は上手に出来ません!もちろんここに今日来てくれた先生たちも最初は下手でした。でも毎日練習して努力して今があります。皆さんも今日ここで習ったことを是非復習してみてください。」何事にも当てはまる言葉ですよね。肝に銘じておかないと・・・。そう感じました。きっと生徒さんたちもそう思ったんじゃないかな。
2011年10月12日 Posted by s-syokunin at 16:02 │Comments(0) │取材日記
ものづくり教室@静岡学園中学校


凄い綺麗な学校だ!率直にそう思いました。生徒も礼儀正しく明るい子ばかりです。今回は「小座布団」と「印章篆刻」作りを生徒さんが体験。こういった機会でもなければ、なかなか体験出来ないことかな?と僕自身感じていたので、学校へ行くのを非常に楽しみにしていました。
小座布団作りでは、ちょっと作り方を聞いて「それでは、始めましょう!」といった感じで簡単に始められると思っていたのですが、職人さんの話を聞いてちょっと反省してしまいました。
職人さんは、座布団の中身の「綿」の栽培地域がインドをはじめ南米、中国などその産地、品種、栽培方法などによってさまざまあること。インドでは綿を綿花から摘む作業をしている多くが10歳~生徒達と同じ年齢の子供たちであること。その子供たちが一日一生懸命働いても日本円で約10円くらいしかもらえないといった話を生徒達に教えていました。
生徒達も製品が出来るまでの過程。原料である「綿」ががどのようにして生産され、どういった経路をたどって日本に届いているのかといったことを真剣に聞き入っていました。







座布団。正直、僕自身も作ったことがありません。なので、今回の「小座布団作り」にチャレンジする生徒達が非常に羨ましかった~。生徒達は、薄く広げられた「綿」を職人さんの指示通り重ねていきながら、徐々に厚みのある座布団の形にしていきます。生徒達から「おぉー!すごい!形になってきた」「先生(職人さんのこと)!ここはどうしたらいいですか?教えてください!」と皆、初めてつくる(ほとんどの生徒がそう思われますが)座布団作りに興奮気味。。
座布団の形に作られた袋に綿を上手く隅までつめる作業では、
見ていると簡単?・・・やってみると、「あれ?!」
さっき、職人さんはいとも簡単にできていたのに・・
生徒達は、自分たちが体験してみて初めて職人さんの熟練された『技』に気付いていたようです。
生徒達は、座布団の出来ていく過程が面白くてたまらない様子。
また、そんな楽しんでいる生徒達を優しく見守る職人さんもとっても嬉しそう。
生徒から
「先生(職人さん)!これもお願いしてよいですか~」とやや甘える感じでお願いする場面も。
でも、さすが女性の職人さん!そんな生徒の声に
「あれ~?私がさっきやったところまでしか出来てないようだけど・・・どういうことかな?糸も足りてないような・・・(苦笑)ハイ!そこまで解いてもう一回!」とやんわりと釘をさしておりました。
そんな和気あいあいとした雰囲気の中、生徒達も最後まで諦めずにやり遂げていました。
完成した座布団の行き先を
「自分で使おうか?お婆ちゃんのところへもって行ってあげようか?でも使ってくれるかなぁ?」
と悩む生徒も。お婆ちゃんにプレゼントしたら、それはきっと喜んでくれるよ~!なんて心でつぶやいたりして。みんな、自分の作品にそれぞれの「想い」を持ちながら満足げな顔つきでした。







「印章篆刻」(いんしょうてんこく)。印鑑を作る体験の生徒達は、みんなアイデアがいっぱい。最初は彫る作業に戸惑っていた様子でしたが、練習の段階でコツを覚えると瞬く間に作品を完成。
生徒にお願いして、自分の印章も作ってもらいたい!と思うほど素晴らしい作品ばかりでした。