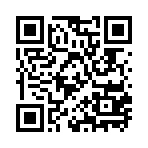静岡県日本調理技能士会会長 高橋治男さんの取材
熱海出身の高橋さんは中学卒業後おじさんが営む魚屋さんに就職されたそうです。熱海の旅館に魚介類を卸していたので配達をしながら旅館の料理人の方たちの技を見て「いつか自分も料理人になりたい!」という気持ちが強くなったそうです。現在は伊東市にある(財)日本書道教育学会東洋文化不二研修場にて調理担当顧問をされています。
お客様に喜んでもらえるように目で見て楽しみ、食べて美味しい、そして旬のものを揃えた材料へのこだわりも忘れない。当然の事ながら衛生面においては最善の注意を払います。美味しくてみんなが喜ぶ料理をこれからも作っていただきたいと思いました。「高橋さん、ありがとうございました。」
「一筋」この言葉が高橋さんが一番好きな言葉だそうです!





ちなみにこの炊飯器3升炊けるそうですよ(驚)
お客様に喜んでもらえるように目で見て楽しみ、食べて美味しい、そして旬のものを揃えた材料へのこだわりも忘れない。当然の事ながら衛生面においては最善の注意を払います。美味しくてみんなが喜ぶ料理をこれからも作っていただきたいと思いました。「高橋さん、ありがとうございました。」
「一筋」この言葉が高橋さんが一番好きな言葉だそうです!





ちなみにこの炊飯器3升炊けるそうですよ(驚)
2012年01月23日 Posted by s-syokunin at 17:00 │Comments(0) │取材日記
WAZAフェスタ2011の動画もアップ!
10月29日30日 WAZAフェスタ 2011inしずおか 開催
10月29日(土)・30日(日)、ツインメッセ静岡で
『WAZAフェスタ 2011 in しずおか』が開催されました。

『WAZAフェスタ 2011 in しずおか』では、アートモザイク、木工や洋裁など様々な業種の職人さん達に教えて貰いながら、ものづくり体験ができる「WAZA体験コーナー」やものづくりを通じて交流を深める「WAZAの交流広場」など子供から大人まで楽しめるイベントが盛りだくさんでした。
他、会場内には以下のような競技大会や様々なコーナーがありました。
・WAZA体験コーナー
・WAZAの交流広場
・農産物加工品展示・販売コーナー
・小中学生技能競技大会
・障害者技能競技大会
『WAZA体験コーナー』では、

「アートモザイク」体験があり、小さな女の子が職人さんからアドバイスを聞き、自分だけのイメージをタイルの破片を用いて描いていました。
その制作中の彼女の横顔は、ハッとするほど真剣な眼差し。やはり、制作中は大人も子供も関係なし。
職人さんに負けず劣らずの意気込みと一生懸命さが伝わってきました。


他、「印章業協同組合」ブースでは『テン刻体験』というものがありました。
このブースは、柔らかい素材の石で自分の名前を彫刻刀を使って彫っていく体験コーナーです。
体験者は小学生低学年の児童から60歳過ぎの年長者までが並んで体験していました。


今回のこのイベント、来場・参加した児童も真剣でしたが我が子を連れてきた親御さんの方が真剣になって体験していたりする場面もありました。
「集まれ!ものづくりキッズ つくるってたのしい」がこのイベントのキャッチプレーズでしたが、『ものをつくる』って大人も子供も童心にかえる良い空間なのかもしれません。
また、『テン刻体験』でのご家族ではお父さんとお母さんが息子・娘の後ろに立ち必死にアドバイス。最終的にお父さんとお母さんが息子・娘の代わりに彫刻刀を持って成果物を子供に自慢していた場面などなど。
『もの』を『つくる』ことで、「家族の和もつくる」。そんな暖かい光景も見ることができた1日でした。
『WAZAフェスタ 2011 in しずおか』が開催されました。
『WAZAフェスタ 2011 in しずおか』では、アートモザイク、木工や洋裁など様々な業種の職人さん達に教えて貰いながら、ものづくり体験ができる「WAZA体験コーナー」やものづくりを通じて交流を深める「WAZAの交流広場」など子供から大人まで楽しめるイベントが盛りだくさんでした。
他、会場内には以下のような競技大会や様々なコーナーがありました。
・WAZA体験コーナー
・WAZAの交流広場
・農産物加工品展示・販売コーナー
・小中学生技能競技大会
・障害者技能競技大会
『WAZA体験コーナー』では、
「アートモザイク」体験があり、小さな女の子が職人さんからアドバイスを聞き、自分だけのイメージをタイルの破片を用いて描いていました。
その制作中の彼女の横顔は、ハッとするほど真剣な眼差し。やはり、制作中は大人も子供も関係なし。
職人さんに負けず劣らずの意気込みと一生懸命さが伝わってきました。
他、「印章業協同組合」ブースでは『テン刻体験』というものがありました。
このブースは、柔らかい素材の石で自分の名前を彫刻刀を使って彫っていく体験コーナーです。
体験者は小学生低学年の児童から60歳過ぎの年長者までが並んで体験していました。
今回のこのイベント、来場・参加した児童も真剣でしたが我が子を連れてきた親御さんの方が真剣になって体験していたりする場面もありました。
「集まれ!ものづくりキッズ つくるってたのしい」がこのイベントのキャッチプレーズでしたが、『ものをつくる』って大人も子供も童心にかえる良い空間なのかもしれません。
また、『テン刻体験』でのご家族ではお父さんとお母さんが息子・娘の後ろに立ち必死にアドバイス。最終的にお父さんとお母さんが息子・娘の代わりに彫刻刀を持って成果物を子供に自慢していた場面などなど。
『もの』を『つくる』ことで、「家族の和もつくる」。そんな暖かい光景も見ることができた1日でした。
2011年10月30日 Posted by s-syokunin at 17:00 │Comments(0) │取材日記
左官職人の萩原多助さん取材

藤枝出身の萩原さん、お父さんと一緒に16歳から見習いとして始めたそうです。それから程なく18歳のときに鉄筋関連の建設現場で今後の日本の建築業界で必要なノウハウを学ぶために単身で東京に向かいました。たまたま行きの電車の中で知り合った方が萩原さんの指のタコを見て声をかけてくれ、3年間その人の下で働いて静岡に戻ってきたという話を聞き、人との偶然な出会いが実は人生の方向性を決める重要なターニングポイントになる事もあるんだと、出会いの大切さを感じました。
今回はツインメッセの西館1Fの技能高等学校実習場で話を伺いました。このとき生徒さんも3名、職人技術を上げ資格試験にパスできるように実践練習をしていました。

実践練習用の壁、つまり資格の課題のために作られたもので、日々練習をすることによって資格試験の当日に緊張しすぎて真っ白にならない為に・・との配慮からのようです。(とはいっても緊張はするようですけど)。

丁寧に捏ねられた土をコテで滑らかに壁に塗っていく様子は「あれ?そんな簡単に?」と思うほど見ている人が簡単に出来るんじゃないかという錯覚を起こすくらい、何十年もこの仕事をされてきた経験が僕たちを勘違いさせます。
いざコテを持ってみて土を捏ねようとしても。
コテに土をすくって壁に塗りつけようとしても。
「あれ?」そうまったくイメージトレーニングは役に立たないようです。

萩原さんが言っていました。仕事は目で盗んで覚えるもの。上手い先輩の作業をよく見て覚えて、そして練習をする。誰も忙しいときに教えてなんてくれない。先輩たちもそうして技を磨いてきたんですよ。
また、そこから今度は人に負けないものを必ず2つから3つ持つことで周りから認めてもらえるようになる。そしていつも心に「初心忘れず」を持ち続けることが大切だそうです。



2011年10月14日 Posted by s-syokunin at 10:36 │Comments(0) │取材日記
静岡県技能競技大会 配管職種
我々素人からの眼で見るとなかなか完成品の見た目での差は分かりませんが、厳しい教官の目はしっかりとマイナスになるポイントは見えていますから、その目が近くにある環境は普段の仕事での緊張感とまた違うストレスにもなったと思います。教官に話を聞くと、もちろん完成品の配管がしっかり出来ているか?水漏れはしていないか?も当然検査します。ただその前にも服装や作業態度などもしっかり減点の対象になりますからって教えていただきました。ただ完成品を作るだけじゃなく、そのものを作る人そしてその過程も非常に大切なんですね。